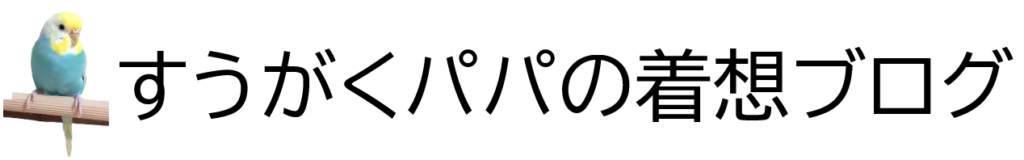こんにちは!
このブログ「すうがくパパの着想ブログ」を読んでくれて、ありがとうございます。
このブログでは、高校受験に向けて数学をがんばっている中学生のみなさんに向けて、数学の「考え方のコツ」や「問題をどう解き始めるか」などをわかりやすく紹介していきます。
Contents
数学の問題、「どうやって解き始める?」って悩んでいませんか?
テストや入試の数学の問題で、
「計算はできるけど、何をすればいいか分からない」
「問題文を読んだ瞬間にフリーズしてしまう…」
そんな経験、ありませんか?
実は、それってあなただけじゃありません。
とても多くの人が、同じことで悩んでいます。
カギは「着想力(ちゃくそうりょく)」にあります
このブログでいちばん大事にしているのが、「着想」という考え方です。
着想とは、問題の“カギ”に気づく力のこと。
たとえば…
- 式に変形するためのヒントを見つける
- 図形を補助線でスッキリさせる
- 規則性の問題で“はじめの一歩”をどう踏み出すか
などなど、「どうやって考え始めるか」を見つけるのが“着想”なんです。
このブログでできること
このブログでは、着想力アップのための情報を、ジャンルに分けて次の三つのコーナーでお届けしています。
着想のタネ
- 身近な数式・図形・数列・定理などを題材に、「なぜその公式が成り立つのか」「どこに着目すれば解法がひらめくのか」を深掘り。
- 直感的に理解できて、1記事5分程度で読める記事にまとめます。
実践!着想トレーニング
- 数式問題、関数、平面図形、立体図形、順列と確率など各分野から代表的な問題を選び、「着想の方法」を解説。
- 問題の水準は偏差値60~65を目指しているぐらいのレベル。
- PDFにノート形式(B5判)でまとめているので、プリントアウトして、実戦演習の教材として活用できます!
数学の勉強方法について
- 数学の問題を解くときの「着想」のしかたについて具体的に解説。
- また、効果的な勉強方法として、ノートの活用術、模試復習のコツ、試験当日の時間配分なども取り上げたいと思います。
- みなさんから寄せられた「着想」のアイデアもこちらで紹介できたらと考えています。
「すうがくパパ」ってどんな人?
私は高校1年と小学5年の二人のムスコがいる父親です(2025年5月現在)。教育関係者ではありません。(2024年の)10月から4ヶ月半、週末と冬休みに長男の受験勉強を手伝いました。
当初ムスコは数学が苦手で模試の偏差値が50未満でしたが、「解き方」ではなく「着想」から考える学習法で立て直し、第一志望グループの高校(偏差値60~65)に合格できました。
ムスコと一緒に入試問題に取り組むうちに、数学の「考え方のトレーニング」ってとても大事だな、と実感しました。
計算力だけじゃなく、“ひらめき力”を育てるには、ちょっとした工夫が必要。
そのヒントを、みなさんにもシェアしたいと思ってこのブログを作りました。
さあ、数学の「着想力」をみがいていきましょう!
高校受験は、たしかに大きな壁です。
でも、ちゃんと準備すれば、数学は「苦手」から「得意」に変えられます。
このブログが、みなさんの「着想力」をみがく手助けになればうれしいです。
これからいっしょに、がんばっていきましょう!